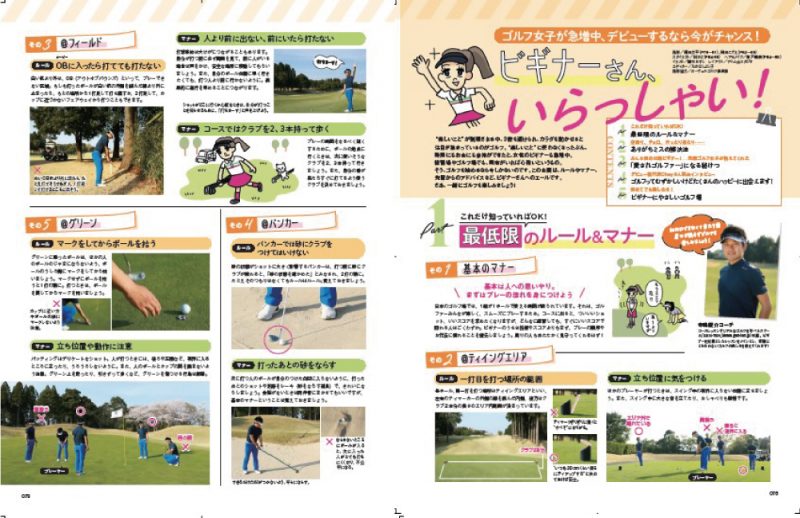ゴルフレッスンの現場では、「意識しているのにスイングが変わらない」という悩みをよく耳にします。
「なぜかダウンスイングから体が伸び上がってしまう」
「手首の角度を維持しようと意識してるのに伸びてしまう」
「体重移動を意識しているのに、できてないと言われる」
この“意識と動作のズレ”は、実は人間の脳の仕組みそのものに起因していることが分かってきています。
「意識」よりも「無意識」が動作を支配している
脳神経科学では、運動の多くは無意識下で制御されていることが知られています。
たとえば、リベットの実験(Libet et al.,1983)*1では、私たちの行動の多くは、意識ではなく無意識によって動かされているという結果が示されています(意識が行動を決定するより前に、脳はすでに動作を始めている)。また、トップアスリートの動作分析においても、「無意識のうちに繰り返された身体の感覚」がプレーの質を支えているという報告が多く見られます。
つまり、「意識して動きを変えよう」とするアプローチは、そもそも脳の自然な制御プロセスとはズレが生じやすいのです。
「わかりやすい説明」ほど誤解を生む
「肩を90度回す」「インパクトは左足体重で」など、明快な説明が必ずしも正解とは限りません。これらは“動作を後から言語化した説明”であり、実際の運動はもっと複雑で立体的なものです。
たとえば、動作学者のニコライ・ベルンシュタイン(Bernstein, 1967)*2の理論によれば、人間の身体動作は「冗長性(redundancy)」を持ち、同じ結果を生むための身体の動かし方は無数にあるとされています。
ゴルフにおいても同じ打球の結果を生むためにも、実はさまざまな身体の使い方が存在しているのです。
つまり、「こう動かせばこうなる」という単純な説明では、本来の動作の幅や可能性を狭めてしまうことがあります。
実はキャッチーでわかりやすい説明ほど、私たちの身体が持つ“自由さ”を見落としてしまうかもしれません。
抽象的な表現がヒントになる理由
「フワッと打つ感じ」や「クラブに任せるように」などの抽象的な表現は、論理的には分かりづらいかもしれません。
しかし、心理学者ダニエル・カーネマン(Kahneman, 2011)*3が提唱した「システム1(直感)とシステム2(論理)」の理論から見ると、こうした表現は“直感的な身体感覚”を引き出すうえで有効と考えられます。
直感的に身体を動かす力を育てるには、「先に意味を考えずに、まずやってみる」という姿勢が大切だと思ってます。
解釈せず、まず“まねる”
以前に記事で紹介したように「コーチの言うことは〇〇プロが言ってるようなこういうことですよね?」と、自分なりの知見の中にしかない解釈と絡めて理解しようとすることは、意外と危険です。コーチの意図とズレた解釈になってしまうと、本来の目的から外れてしまうからです。
ゴルフ上手はマネ上手
これを「トップダウン処理」と呼び、自分の過去の経験や知識に基づいて物事を解釈する脳の働きと説明されます。もしこういう思考のクセがあると自覚した方はレッスンを受ける時に「いま、自分なりの解釈をしてはないだろうか?」と問いかけるようにしてみましょう。
正解は、私たちの“想像の外側”にある

何かを学ぶとき、私たちは「すぐに結果を出したい」と思いがちです。
でも、正解は一度の説明で得られるものではなく、試行錯誤のなかで少しずつ感覚として理解されていくものです。私たちはつい「分かりやすい説明」や「自分なりの解釈」に安心感を求めてしまいます。でも、ゴルフのように“感覚”が左右するスポーツでは、頭の中で思い描ける範囲=正解とは限りません。
「むしろ、正解はいつも、自分の想像の外側にある。」
だからこそ、「よくわからないけど、ちょっとやってみよう」とか、「なんか今はまだ腑に落ちないけれど、とりあえずやり続けてみよう」といった柔らかい姿勢が、上達の扉を開いてくれます。
分からなくていい。すぐにできなくていい。それでも、一歩ずつ「知らなかった自分」に出会いながら、スイングのスキルやゴルフの内容が確実に変わっていきます。
そんな過程こそが、ゴルフの本当の面白さに気づくきっかけになるのかもしれませんね。
-参考文献-
*1 Libet, B., Gleason, C. A., Wright, E. W., & Pearl, D. K.(1983)
*2 Bernstein, N. A. (1967). The Coordination and Regulation of Movements.
*3 Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow.